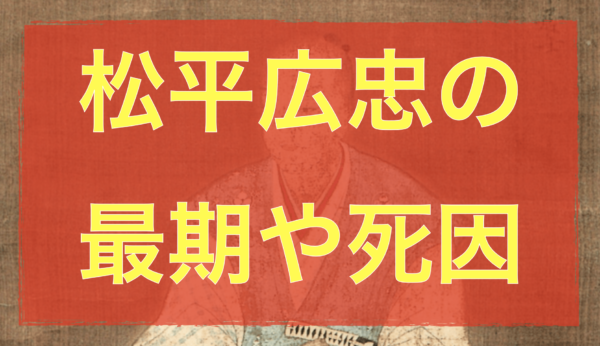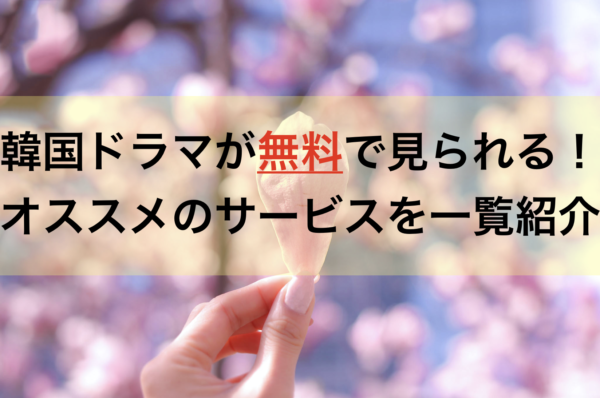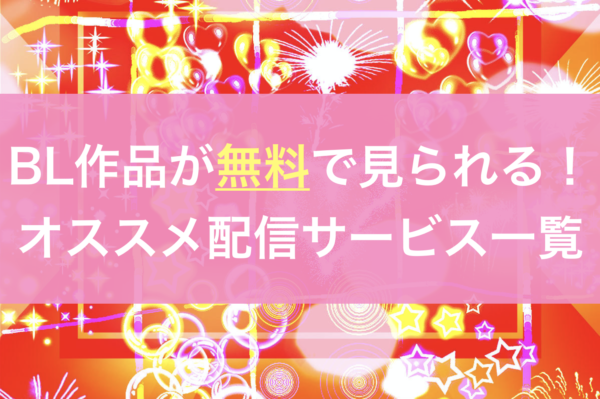松平広忠は徳川家康の父にあたる人物ですが、実の息子である家康を人質に出してしまうような冷酷非道な性格というイメージがあります。
今回は、松平広忠の最後・最期はどのようであったのか、死因について解説します。
また、信長に殺されたという話や殺害方法とその理由、徳川家にまつわる脇差についても見ていきます。
松平広忠の最後・最期の流れと死因
松平広忠の最後・最期の流れや死因とされているさまざまな説について見ていきましょう。
松平広忠の最後・最期の流れ:若くして死亡
徳川家康の父、松平広忠は24歳の若さで亡くなりましたが、その生涯で最大の敵は織田信長の父・信秀でした。
広忠は少年期から亡くなる直前まで、三河(現在の愛知県東部地方)へ勢力を拡大しようとしていた信秀に苦しめられ続けました。
まず、広忠がわずか10歳で松平家を継ぎ、自分の本拠地であった岡崎城を奪われて逃亡生活を送る事になったのも、広忠の父・清康が、信秀との戦いの最中に家臣の裏切りによって死亡した事が原因でした。
そして広忠が大人になり岡崎城を取り戻した後は、自分の領地を守るために何度も信秀と戦っています。
天文16年(1547年)には織田軍によって岡崎城を落とされ、協力関係にあった今川家に援軍を求めました。
この時、広忠は今川家に息子の竹千代(後の家康)を人質に出したのですが、護送中に竹千代が織田家に奪われてしまうという事件が発生しました。
その後、竹千代は織田家で人質としての生活を送る事になりますが、信秀は天文17年(1548年)に再び三河地方へ攻めてきました。
これにより「小豆坂の戦い」と呼ばれる大きな戦いが起こりましたが、広忠は今川家と協力し、今度は織田軍を追い返しました。
この「小豆坂の戦い」には、実は美濃(現在の岐阜県南部地方)の斎藤道三が関わっていたという説があります。
当時は道三も信秀と敵対しており、道三の協力を得て広忠が対織田家の軍を出した事が原因となり、信秀は三河へ攻めこんだという説です。
このように広忠は周辺の武将達と協力して、なんとか信秀に抵抗を続けていました。
しかし息子の竹千代は織田家の人質となったまま、天文18年(1549年)3月6日に広忠は亡くなりました。
広忠の死に関しては多くの記録が残っていますが、資料ごとに死因が違っており、どれが本当なのかはっきりしていません。
松平広忠の死因:3つの死亡説
|
|
|
では松平広忠の死因について、詳しく見ていきましょう。
彼の死因として記録されているのは
- 病死(『松平記』など)
- 家臣であった岩松八弥という人物に殺害された(『岡崎領主古記』など)
- 一揆により殺害された(『三河東泉記』など)
の3つです。
この内、もっとも多くの資料で死因とされているのは「病死」です。
しかし病死と書かれている記録は、すべて江戸時代以降に書かれたもので、その大半が徳川家康に関連する事柄や、家康の家系などを記した記録です。
一方で広忠の地元である三河地方に残された記録には、広忠は殺害されたと書かれています。
更に広忠の死に関して、「病気で亡くなった」としか書かれておらず、亡くなる直前はどんな状態だったのか、詳しい病状や病名などは一切書かれていません。
また、広忠は24歳という若さで亡くなっているため、病死はかなり珍しいと言えます。
そして天文18年(1549年)2月20日、つまり亡くなる2週間ほど前にも織田家と戦ったという記録が残っています。
戦でのケガが原因で病気にかかって死亡した可能性や、急病だった可能性もありますが、病状についての記録がない事は、とても不自然だと感じます。
更に、広忠の死因を病死としている記録にも、八弥に襲われた事件のことが書かれています。
これらの記録では、広忠が襲われた時期は亡くなる2年~4年前となっていますが、「八弥に斬られた傷が元で病死した」とされているものもあります。
以上のことから、広忠は殺害された可能性が高いと考えられます。
家康に関係する多くの資料で広忠の死因が病死とされている事については、江戸幕府初代将軍の父が家臣に殺害されたのは不名誉な事だと考え、病死と記録したと考えれば納得がいきます。
|
|
|
松平広忠が信長に殺害・殺された理由や脇差と徳川家
松平広忠が信長に殺害・殺された理由、その説がありえるのか?
また、脇差と徳川家に災をもたらす村正伝説について見ていきましょう。
松平広忠が信長に殺害・殺された理由
大河ドラマ「麒麟がくる」では、松平広忠を殺した犯人が織田信長であったことも衝撃的でした。
信長は後に徳川家康と同盟を結び、織田家と徳川家は強い協力関係にあったため、家康の父を殺す事など無いように思えます。
果たして、信長が広忠を殺害した可能性はあるのでしょうか。
そして信長が犯人なのであれば、その理由は何だったのでしょうか。
広忠が亡くなった天文18(1549年)3月、織田家と今川家の間で三河地方を巡った大きな戦いがありました。
三河地方の織田家の拠点である安祥城に、今川家が約1万の軍勢で攻めてきました。
実は織田家が守る安祥城と、広忠の本拠地である岡崎城の距離は約7kmしかありません。
もし岡崎城の戦力が今川家に加勢できなくなれば、安祥城はかなり守りやすくなるはずです。
信長であれば、戦の支度で忙しい父の代わりにこの状況を何とかしようと考えてもおかしくないでしょう。
この戦いの直前、信長は斎藤道三の娘と結婚したことで、織田家の後継ぎとなる可能性が高くなりました。
そこで、自分が後継ぎとして相応しい事をアピールするためにも、信長が広忠の暗殺を考えた可能性はあります。
また、広忠が岩松八弥に襲われた事件について「八弥は隣国の策略によって広忠を刺した」と記されている記録があります。(『武徳大成記』)
松平家の治めている三河と接しているのは、尾張(現在の愛知県西部地方)、遠江(現在の静岡県西部地方)、信濃(現在の長野県)です。
この内、遠江は協力関係にある今川家の領地です。
そして信濃には武田信玄が攻め込んでおり、信濃各地の領主はその対応に追われ、三河に目を向ける余裕はありませんでした。
そのため「隣国」とは尾張しか考えられず、広忠を殺す動機が一番強いのも織田家でした。
更に、一揆により殺害されたとなっている記録には、「一揆の原因は織田信秀の策略」と書かれています。
これらの記録や、当時の織田家と松平家の関係から考えれば、信秀・信長親子のどちらかによって殺されたという考え方は、かなり自然であると思います。
松平広忠の脇差と徳川家:形見と村正の呪い
そして「麒麟がくる」では、脇差が広忠の形見として届けられるシーンがありました。
実際には広忠の脇差は残されておらず、このシーンに関してはドラマを盛り上げるための創作だと言えます。
しかし広忠の殺害と脇差に関しては、興味深いエピソードがあります。
広忠は岩松八弥に襲われた際、脇差で刺されたそうですが、この脇差は村正という職人に作られた刀だと言われています。
実は広忠の父・清康を斬り殺したのも村正の刀だったそうです。
こういった経緯から村正の刀は徳川家に災いをもたらすと言われ、江戸時代には妖刀村正伝説として、歌舞伎や浮世絵などの創作物で取り上げられるようになりました。
大河ドラマの脚本も、この話をふまえた上で書かれたものではないでしょうか。
実際は広忠の殺害に使われた可能性のある脇差を、広忠の無念な気持ちを伝えるために形見の品物として選んだのだと思います。
広忠の代では敵対関係であった松平家と織田家ですが、息子の家康と信長の代には強力な同盟相手となりました。
そのため広忠の殺害に織田家が関わっていたとしても、家康は信長に気をつかって、真相を深く追求できなかったのではないでしょうか。
信長と良好な関係を続けた事が家康の天下へ繋がった事を考えると、広忠は両家の関係改善のために損な役回りを引き受けることになった、可哀想な人物だったという印象を受けます。
しかし、広忠が周りの勢力と協力する事で領地を守りぬいた姿を見ていた家康は、情にこだわる事よりも、同盟関係を大切にして家を盛り立てて行くことを選択したのでは無いでしょうか。
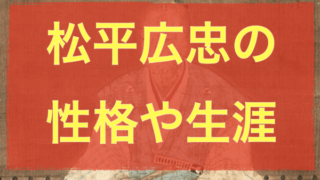
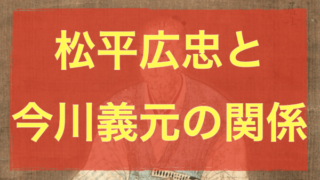
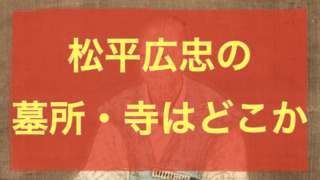
まとめ
・松平広忠の最後・最期の流れ:若くして死亡
息子の竹千代は織田家の人質となったまま、天文18年(1549年)3月6日に広忠は亡くなりました。
・松平広忠の死因:3つの死亡説
|
|
|
松平広忠のの死因として記録されているのは
- 病死(『松平記』など)
- 家臣であった岩松八弥という人物に殺害された(『岡崎領主古記』など)
- 一揆により殺害された(『三河東泉記』など)
の3つです。
・松平広忠が信長に殺害・殺された理由
自分が後継ぎとして相応しい事をアピールするためにも、信長が広忠の暗殺を考えた可能性はあります。
・松平広忠の脇差と徳川家:形見と村正の呪い
実際には広忠の脇差は残されておらず、このシーンに関してはドラマを盛り上げるための創作だと言えます。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。他にも様々な情報がありましたら、またコメント欄に書いてくださるとうれしいです。