紀貫之の「土佐日記」は中学校・高校のいずれでも扱われることが多い作品です。
内容自体は旅日記を男なのに女のフリをし、さらにジョークを交えて執筆しているだけなのですが、古文の慣れない言い回しや高校になると品詞分解などやることが増えるので苦手意識を持つかもしれません。
今回は、そんな「土佐日記」の冒頭部分「馬のはなむけ」や「門出」と呼ばれる部分の古語の語句・漢字の意味調べと語句の読み方を完全版として一覧にまとめてみます。
土佐日記「馬のはなむけ・門出」とは
紀貫之の土佐日記「馬のはなむけ・門出」とは何なのか、紀貫之とはどういう人物ですごかったのかをなんとなく頭に入れておくと現代語訳や要約の際にも役立ちますし、テストでも本筋を忘れない解答ができるようになります。
土佐日記や紀貫之とは
土佐日記は平安時代に役人・紀貫之が土佐(今の高知県)に転勤させられ、ようやく高知県での勤務から解かれて帰京するという道中での出来事や思ったことを書いたものです。
土佐日記は、高知県を出発する12月21日から始まり、2月16日の京都への到着日まで続きます。
役人の記す日報のように形式張ったものが当たり前だった時代に、男なのに女のフリをし、さらにただひたすらに思ったことを主観をガッツリ入れ、紀貫之なりのジョークも交えて書いたという部分が衝撃的な問題作となりました。
- 文章と言えば漢字・漢文
- 文章は男が書くもの
- 硬い文章を書いて当たり前
といった当時の常識を打ち砕いたことで、女流文学や日記調の読みやすい文章を書いてもよいという環境が育まれるきっかけになりました。
土佐日記「馬のはなむけ・門出」とはどこまでか
土佐日記「馬のはなむけ・門出」は、教科書によっては
- 土佐日記
- 馬のはなむけ
- 土佐日記・門出
など、さまざまな呼び方をされています。
ここでは、できるだけ漏れがないようにするため冒頭の「男もすなる〜」から始まり、24日目の「〜足は十文字に踏みてぞ遊ぶ。」までの語句の意味や読み方を解説していきます。
土佐日記「馬のはなむけ・門出」語句・漢字の意味や読み方完全一覧!
では、土佐日記「馬のはなむけ・門出」の語句・漢字の意味や読み方を一覧にしてまとめていきます。
基本的には日にちごとに分けて解説しています。
複数意味があるものは、当てはまるものを太字にしています。
男(をとこ)もすなる日記(にき)といふもの
| 語句・漢字 | 読み方 | 意味 |
| 男 | をとこ | 男 |
| 日記 | にき | 日記 |
| 女 | をんな | 女 |
| 十二月 | しはす | 12月 |
| 二十日余り一日 | はつかあまりひとひ | 21日 |
| 戌の時 | いぬのとき | 午後8時ごろ/午後7時〜9時の間 |
| 門出す | かどです | 出発すること/仮の出発 |
| そのよし | その状況 | |
| いささかに | ほんの少し、ちょっと | |
| 書きつく | かきつく | 書きつける、書き記す |
| ある人 | あるひと | (文中では)紀貫之 |
| 県 | あがた | 国司などの任用地 |
| 四年五年 | よとせ いつとせ | 4、5年 |
| 果てて | はてて | 終わる、修了する/死ぬ、息を引き取る |
| 例のことども | れいのことども | 後任者への引き継ぎ |
| みな | すべて、全部 | |
| 解由 | げゆ | 解由状(事務引き継ぎ文書)/交代手続きのこと |
| 住む館 | すむたち | 住んでいた官舎 |
| 乗るべき所 | のるべきところ | 乗ることになっている場所 |
| 渡る | わたる | 移動する |
| かれこれ | あの人この人と/あれやこれや、いろいろ | |
| 知る知らぬ送りす | しるしらぬおくりす | 知っている人や知らない人が見送りする(準体法) |
| 年ごろ | としごろ | 長年の間 |
| くらべつる | 親しい/比較する/競う | |
| 日しきりに | ひしきりに | 一日中 |
| とかく | あれこれ/ともすれば/とにかく、いずれにしても | |
| ののしる | 大声で騒ぐ/(動物が)吠える/評判が良い/勢いがある/罵倒する/大いに〜する | |
| 夜 | よ | 夜 |
二十二日に、和泉の国までとたひらかに願立つ
| 語句・漢字 | 読み方 | 意味 |
| 二十二日 | はつかあまりふつか | 22日 |
| 和泉の国 | いづみ | (現在の大阪府南部) |
| たひらかに | 無事であるように/平ら/おだやか | |
| 願立つ | ぐわんたつ | 神様に祈る |
| 藤原のときざね | ふじわらのときざね | 藤原時実 |
| 船路 | ふなぢ | 船旅 |
| 馬のはなむけ | むまのはなむけ | 旅立つ人に、プレゼントやお金を渡したり送別会・宴を開くこと |
| 上中下 | かみなかしも | 身分が高い人も、中くらいの人も、低い人もみんな |
| 酔ひ飽き | ゑひあき | ひどく酔っ払う |
| いと | たいへん、とても | |
| あやしく | 見苦しい/身分が低い/不思議/おかしい/珍しい/異常/不都合/不安 | |
| 潮海のほとり | しほうみのほとり | 海辺 |
| あざれあへり | ふざけあっている | |
| ※あざる | ふざける/腐る |
二十三日、八木のやすのりといふ人あり
| 語句・漢字 | 読み方 | 意味 |
| 二十三日 | はつかあまりみか | 23日 |
| 八木のやすのり | やぎのやすのり | |
| 国 | くに | 国府 |
| 言ひ使ふ者 | 召し使う人 | |
| あらざなり | 〜ないようだ/〜ないそうだ | |
| たたはしき | 威厳がある/満ち足りている | |
| 守柄 | かみがら | 国守の人柄 |
| 国人 | くにひと | その土地に住む人 |
| 物 | 選別としてもらった品物 |
二十四日。講師、馬のはなむけしに出でませり。
| 語句・漢字 | 読み方 | 意味 |
| 二十四日 | はつかあまりよか | 24日 |
| 講師 | かうじ | 国分寺の僧侶 |
| 出でませり | いでませり | おいでくださった/いらっしゃった |
| ありとある | その場にいるすべての | |
| 上下 | かみしも | 身分の高い者も、低い者も |
| 童 | わらは | 子供 |
| 酔ひしれて | 酒に酔って正体がなくなって | |
| 一文字 | いちもんじ | 「一」という最も簡単な文字 |
| しが足 | その足 | |
| 十文字に踏みてぞ遊ぶ | じふもんじにふみてぞあそぶ | 十の字の形のように踏んで遊ぶ。 |
まとめ
・土佐日記や紀貫之とは
土佐日記は、高知県を出発する12月21日から始まり、2月16日の京都への到着日まで続きます。
・土佐日記「馬のはなむけ・門出」とはどこまでか
ここでは、できるだけ漏れがないようにするため冒頭の「男もすなる〜」から始まり、24日目の「〜足は十文字に踏みてぞ遊ぶ。」までの語句の意味や読み方を解説していきます。
・土佐日記「馬のはなむけ・門出」語句・漢字の意味や読み方完全一覧!
土佐日記「馬のはなむけ・門出」を4つのブロックに分けて語句・漢字の意味や読み方を紹介しています。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。他にも様々な情報がありましたら、またコメント欄に書いてくださるとうれしいです。
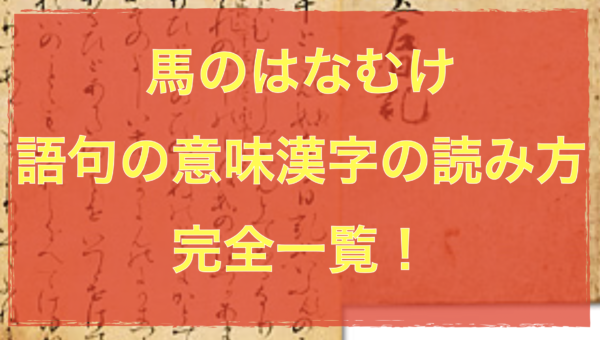
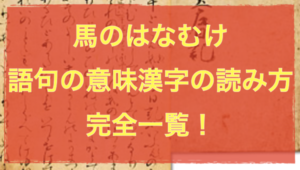
コメント