今川義元は織田信長を描いた作品で、無能な武将のようなイメージを持ってしまいます。
今回は、今川義元の性格・特徴やエピソード・逸話を紹介します。
いい人なのかや幼少期・政治家としての手腕についても解説します!
今川義元の性格・特徴やイメージ・政治家としての手腕
今川義元の性格・特徴やイメージはどうなのか、政治家としての手腕について見ていきましょう。
今川義元は無能な武将のイメージ
今川義元といえば、桶狭間の戦いで織田信長が倒した武将として知られています。
そのため、公家のような見た目で軟弱な人物として描かれる事が多く、無能な武将だと思われがちです。
しかし2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」では威圧感のある強力な武将として描かれ、驚いた方もいらっしゃると思います。
無能ではなく強力な戦国大名
実際今川義元は、元々は駿河(現在の静岡県中部地方)のみを支配していた今川家を、東海3か国を支配する勢力へ拡大した強力な戦国大名だったのです。
東海3か国とは、駿河・遠江・三河の3国で、現在の静岡県ほぼ全域と愛知県の西部地方におよぶ広い地域です。
これほど大きな勢力を持った大名は、戦国時代を通しても数えるほどしかいません。
元々、今川家は室町幕府の将軍である足利家の分家であり、名目上は足利家の家臣となっていました。
しかし義元は足利家との縁を切り、完全に独立した勢力となる事を宣言しました。
将軍家の力に頼らず、自らの実力で今川家を発展させた、勇敢な武将だった事が分かると思います。
義元は領地経営や外交などの政治的な手腕にも優れていました。
特に有名なのは外交力で、領地が隣り合っていたため争いを続けていた武田信玄、北条氏康と三国同盟を結びました。
これにより東側から攻められる心配がなくなり、三河地方から尾張(現在の愛知県東部地方)へと西へ勢力を拡大する事に専念できるようになりました。
大きな勢力を持つ物同士で手を組んで、支配しやすい地域へと侵攻する手際の良さから、義元の抜け目のない性格が伺えると思います。
今川義元の政治家としての手腕
「麒麟が来る」の主人公、明智光秀が仕える斎藤家は美濃(現在の岐阜県南部)を治めていました。
もし今川家が本格的に西へ攻めてくるならば、いつか美濃も巻き込まれることになります。
つまり光秀や斎藤家の当主・斎藤道三から見ると、今川家はもっとも警戒すべき大名でした。
そしてこれほど強大な勢力を持つ大名に対抗するには美濃の斎藤家だけでは難しく、すでに今川家と領土争いが起こっていた尾張の織田家と同盟を結ぶ動機としても十分なものです。
「海道一の弓取り」や「天下で最も上洛に近い男」などと呼ばれ、周囲に恐れられていた大名、それが今川義元だったのです。
戦国時代の合戦の中でも有名な、武田信玄と上杉謙信が争った川中島の戦いを、仲裁して停戦させることが出来たという事実からも、義元が絶大な力を持っていた事が分かると思います。
今川義元のエピソード・逸話や幼少期
今川義元にまつわるエピソード・逸話を紹介します。
また、今川義元の幼少期の意外な歴史も見ていきましょう。
京都の流行を取り入れる
一般的な今川義元のイメージに近いエピソードとして、京都の流行を取り入れようとしていたことが挙げられます。
戦争によって都から逃れてきた貴族たちを保護したり、京都の貴族や僧侶と交流する事で、義元が治めていた駿河の駿府城下町は、戦国三大文化と呼ばれるほど雅な文化が発達した町になったそうです。
また、自らも貴族のようにお歯黒や薄化粧をしていたとも言われています。
今の感覚からすれば軟弱な印象を受けますが、実は相当格式が高い武家でなければ許されない格好でした。
そして武士が戦場に向かう際に化粧をしていくことは、嗜みの一つであったとも言われています。
そうであれば義元は、常に戦に挑むような緊張感を持って生活をしていた、自分に厳しい人物だったと言えます。
人質だった家康に英才教育をする
徳川家康が幼い頃、今川家の人質になっていたことも有名な話です。
しかし義元は家康を非常に良い待遇で迎えています。
まず、今川家の軍師であり義元の師匠でもある太原雪斎に預け、軍事に関する英才教育を行いました。
そして家康が成人すると刀と鎧を与えました。
義元は家康の才能を見抜いており、今川家の家臣になって働いてもらう事を望んでいたのではないでしょうか。
今川家の家臣団は優秀だったことからも、義元の人を見る目が優れていたことが伺えます。
幼少期は苦労人
更に、かなりの苦労人でもありました。
義元は今川家の五男で生まれた時にはすでに兄が家を継ぐことが決まっており、正室の子ではありましたが、わずか4歳でお寺に預けられました。
その後すぐに出家し、成長した後は京都で修行に励んでいました。
しかし父が亡くなり、今川家を継いだ長兄も若くして死亡。
直後に次兄まで死んでしまったため、今川家の中で跡継ぎを巡った争いが起こります。
結局、異母兄と義元が当主の座を争って戦いになり、この戦いに勝利して今川家を継いでいます。
義元が今川家を継いだ経緯には疑惑もあります。
跡継ぎ争いの元となった長兄と次兄の死は、なんと同じ日に起こっており、その死因も不明のままです。
そしてこの前年に今川家から義元に対して、京都から戻って来るようにと要請があったため、この時義元は偶然帰国していました。
長兄は病弱であったと言われており、もしかすると義元は父が死んだら当主の座を奪う事を早い段階で決意していたのかもしれません。
実際に策略を巡らせて今川家の当主になったのだとしたら、非常に冷酷な野心家で、用意周到。
そしてチャンスを待つことができる忍耐強い人物だったと言えます。
桶狭間の戦いの宴会の意味:戦意喪失を意図
そして義元が命を落とした桶狭間の戦いでは、油断して宴会を開いていたと言われています。
しかし、これまでの逸話から義元の人物像を考えてみると、実力に裏付けられた自信を持っており、それを周りにアピールする事も欠かさなかった人物だったのではないでしょうか。
ですから桶狭間でも、これだけの余裕があるのだという事を見せつけ、織田家の戦意を喪失させるために宴会を開いていたのではないでしょうか。
それが今川軍が負けたことによって、油断によって命を落としたという話に変わったのではないかと思います。
今川義元は貴族文化にかぶれ、軟弱で、戦国時代を生き抜くだけの器ではなかった人物。
そういったイメージがついてしまったのは、やはり圧倒的な兵力差を覆されて討ち死にした桶狭間の戦いのインパクトが強いからでしょう。
これまでの作品では負けた大名というネガティブなイメージに基づき、脚色して描かれることが多かったのですが、「麒麟がくる」の今川義元はかなり実像に近いと言えそうです。
まとめ
・今川義元は無能な武将のイメージ
公家のような見た目で軟弱な人物として描かれる事が多く、無能な武将だと思われがちです。
・無能ではなく強力な戦国大名
今川義元は、元々は駿河(現在の静岡県中部地方)のみを支配していた今川家を、東海3か国を支配する勢力へ拡大した強力な戦国大名だったのです。
・今川義元の政治家としての手腕
「海道一の弓取り」や「天下で最も上洛に近い男」などと呼ばれ、周囲に恐れられていた大名、それが今川義元だったのです。
・京都の流行を取り入れる
一般的な今川義元のイメージに近いエピソードとして、京都の流行を取り入れようとしていたことが挙げられます。
・人質だった家康に英才教育をする
徳川家康が幼い頃、今川家の人質になっていたことも有名な話です。
しかし義元は家康を非常に良い待遇で迎えています。
・幼少期は苦労人
義元は今川家の五男で生まれた時にはすでに兄が家を継ぐことが決まっており、正室の子ではありましたが、わずか4歳でお寺に預けられました。
・桶狭間の戦いの宴会の意味:戦意喪失を意図
桶狭間でも、これだけの余裕があるのだという事を見せつけ、織田家の戦意を喪失させるために宴会を開いていたのではないでしょうか。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。他にも様々な情報がありましたら、またコメント欄に書いてくださるとうれしいです。
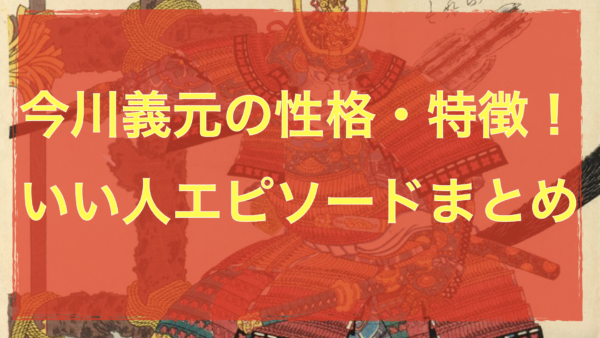
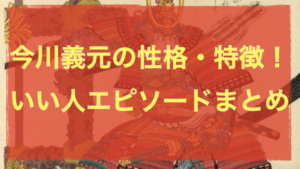
コメント